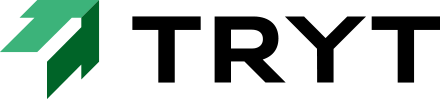介護の枠組みを超え、誰もが感動する介護を-社会福祉法人長寿村 神成 裕介さん
介護の枠組みを超えて、楽しさあふれる世界を創り出す
今回お迎えするのは、国内で100を超える介護施設を運営される社会福祉法人元気村グループ理事長の神成裕介様です。急速に高齢化が進む中、これまで以上に身近になっていく「介護」。業界が抱える現状の課題と見据える未来についてお伺いしました。

—Profile
神成裕介(かんなり ゆうすけ)
2005年に社会福祉法人元気村の理事に就任、2011年6月に社会福祉法人長寿村の理事長に就任後、社会福祉法人元気村・長寿の里・長寿の森・杜の村の理事長に就任。その他、現在複数の介護事業・医療事業・教育事業の運営に尽力している。
―日本は急速な高齢化が進んでいます。労働人口が減少する中で、介護業界における人材不足にどのように向き合っていらっしゃいますか?
介護業界は慢性的な人手不足が続いています。元気村グループでも同じ課題を抱えていますが、人手不足は短期間で解決できる課題ではありませんので、「人の数が多いほど質が向上する」という考え方から、「少人数でも質の高い介護を提供する」、ということを突き詰めていく必要があると感じています。
―少人数で質の高い介護を提供するために、取り組まれていることを教えてください。
従業員が同じ志を持って進むことができる組織づくりを大切にしています。元気村グループでは、「『家族主義』と『現場主義』をモットーに、地域から世界に広がる感動介護を実現し、すべての人が元気に笑顔で楽しく『共に生きる』社会を実現しよう」という理念を掲げています。生まれ育った環境や学んだこと、見聞きしてきたことは人それぞれであり、多様な職員が当社グループでも介護従事者として働いています。そのなかで、理念は皆が同じ志を持って進んでいくための核となるものです。創業から大切にしている「家族主義」「現場主義」「感動介護」「共に生きる」といった姿勢に共感する仲間が集まってくれ、現場や研修などを通じてその想いを一つにしながら介護事業に取り組んでいます。
―『共に生きる』社会の実現のために、介護の現場で必要なことを教えてください。
介護の目的の一つである自立支援をどう捉えるかという発想の転換が重要であると考えています。自立支援とは、一人では難しいことを介護でサポートしながらできることを増やし、ご利用者様に「自分でできる」と意欲的になっていただくための取り組みです。食事や入浴、排泄などの介助は、あくまで介護が持つ機能の一つです。上げ膳据え膳で何もかもをお世話するということではありません。また、日常生活で生き甲斐を叶えるお手伝いをすることも介護の大きな目的だと考えています。
―ご利用者様の「できる」が増えると、職員の方のやりがいにもつながりそうです。
職員はご利用者様に「ありがとう」と感謝していただけることを何より嬉しく感じていますが、もっと嬉しいことは、介護でサポートしたことで、ご利用者様が少しずつ日常生活の中でできる場面が増えていくと、逆に私たちからご利用者様に「ありがとう」と伝えられるように変わっていくことです。職員からも感謝を伝えること、そしてその機会を職員が多く生み出せるようなコミュニケーションを取ることが、本当の「自立支援」につながります。

業務における楽しみは、ご利用者様との日々の会話です。「今日は調子がいい」「家族に誕生日を祝ってもらった」といった話を聞きながら、日々、喜びを分かち合っています。
―介護事業のこれからの可能性をどのように見ていますか?
ご利用者様と職員の誰もが幸せを感じられる介護事業者を目指しています。そのために、介護の枠組みを超えた自由な発想で可能性を広げたいと思っています。地域との連携は社会福祉法人の大きな役割の一つです。
―どのような地域連携が考えられますか?
例えば、地域社会への貢献を目的に介護施設を活用するというアイデアがあります。お祭りのような地域の人が集う場として施設を開放することも、条件が揃えば十分に可能だと思います。或いは、子ども食堂を更に発展させて、ご利用者様と子どもたちが世代を超えて共に食卓を囲む場づくりも考えられるでしょう。地域の方々と共に楽しいプランを実現していくことで、介護のイメージを変える道筋につながると期待しています。
―介護現場の魅力を知っていただくきっかけになりそうです。
ご利用者様と職員の間に流れる楽しげな空気を施設で感じる瞬間が、私にとっての一番の喜びです。ご利用者様が幸せに過ごしていること、職員が充実している喜びを広く分かち合うために、現場目線で楽しさにあふれた介護の世界を築きあげていきたいと考えています。私たちが取り組む介護という仕事は、世の中では大変な仕事と思われていますが、これほど人の人生に貢献できる仕事はなく、これほど意義深い仕事はないと思っています。私たちが日々、目の前のその人に幸せを届けるその積み重ねが、地域、日本、そして世界にまでも元気と笑顔をあふれさせると信じています。